イベント
【イベント報告】 第9回アフリカ開発会議(TICAD 9)へのGHIT Fundの参画
2025年8月20日〜22日にかけて横浜市で開催された第9回アフリカ開発会議(TICAD 9)において、GHIT Fundは9つのテーマ別イベントを主催・共催または登壇者として参画しました。政府関係者、国際機関、研究者、業界の専門家など多様なステークホルダーと連携し、アフリカのグローバルヘルス分野でのイノベーションと公平な医療の推進にについて議論を深めました。
3日間の会期中、GHIT Fundは政府関係者や国際機関、アフリカ諸国の代表者を含む500名以上の参加者と積極的に交流し、国境を超えた知見の共有や協力の機会を築きました。全体の約15%のテーマ別イベントが国際保健やグローバルヘルス課題に焦点を当てており、TICAD 9における医療分野のイノベーションの重要性が際立ちました。GHIT Fundは、これらのテーマ別イベントや展示ブースを通じて、グローバルな対話を促進し、新たなパートナーシップの構築により十分な医療サービスを受けられない人々に革新的な医療のアクセス拡大を推進しました。
本レポートでは、GHIT Fundが参画した主なテーマ別イベント、得られた成果、そして今後の展望についてご紹介します。
医療技術のイノベーションと公平性の新時代
8月20日:GHIT Fundは、国連開発計画(UNDP)、新規医療技術のアクセスと提供に関するパートナーシップ(Access and Delivery Partnership:ADP)と共同(後援:外務省および厚労省)で、医療技術のイノベーションと公平なアクセスをテーマにしたセミナーを開催しました。本イベントには、登壇者に武見敬三氏(元厚生労働大臣)、中村亮氏(外務省地球規模課題審議官兼大使)をはじめ、国会議員、国連幹部、製薬企業のリーダー、アフリカ各国の規制担当官、大学研究者、外交関係者など、幅広い参加者が集いました。
主な議論は、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の推進やパンデミック対策、グローバルヘルスの公平性を前進させるために、技術革新のさらなる強化と、すべての人が公平に医療へアクセスできる仕組みづくりであり、医療を十分に享受できない人々への治療薬やワクチン、診断薬を届けるための戦略的パートナーシップ構築の重要性が強調されました。
特に「デジタル時代における公平な医療技術の研究開発推進」をテーマとしたパネルでは、研究開発とアクセス確保を一体的に考える視点や、アフリカにおける研究体制強化、規制の整合化、デジタル技術の活用、パートナーシップの在り方などが議論され、医療技術のアクセス確保は開発初期段階から検討を始めることの重要性も強調されました。また2019年に発足したGHITと日本政府、UNDPのADPが共同運営する「新規医療技術、アクセスと提供のための協働(Uniting Efforts for Innovation, Access and Delivery: Uniting Efforts)」プラットフォームの活用事例も紹介され、登壇者からは、包括的な資金調達パートナーシップの構築、明確なビジネスモデルによる研究開発ギャップの解消、試験の同時進行で開発を加速する革新的な仕組みへの期待も挙げられました。
また、不安定なグローバルヘルスにおける資金調達の時代では、「ストレスに耐えるだけでなく、むしろ困難からさらに強くなる“アンチフラジャイル”なシステムづくり」の重要性を、GHIT Fund投資戦略アソシエイト ヴァイスプレジデントの浦辺隼が提言しました。

アフリカ共創で拓く健康と経済の未来:官民連携の最前線
8月20日:内閣府および内閣官房主催のイベントでは、官民連携を通じた日本のアフリカ医療分野への貢献を紹介されました。内閣府特命担当大臣 健康・医療政策担当、アフリカ4ヶ国の保健閣僚等、国際金融公社(IFC)、アフリカ開発銀行、一般社団法人 日本経済団体連合会の幹部らが参加し、日本企業によるアフリカとのヘルスケア分野での協力覚書のほか、「TICAD7」で始動した「アフリカ健康構想(AfHWIN)」の進展も取り上げられました。またケニアにおける医療物資の現地生産拡大、基幹病院の医療管理チーム強化のための技術支援、セネガルでの母子保健の改善など、アフリカ各国の閣僚から日本による具体的な投資や協力の成果が報告されました。GHIT Fund CEO國井修は、「希望の大陸・アフリカと、日出ずる国・日本が力を合わせることで、より健康で豊かで平和な世界への道を照らしていきたい」と締めくくりました。
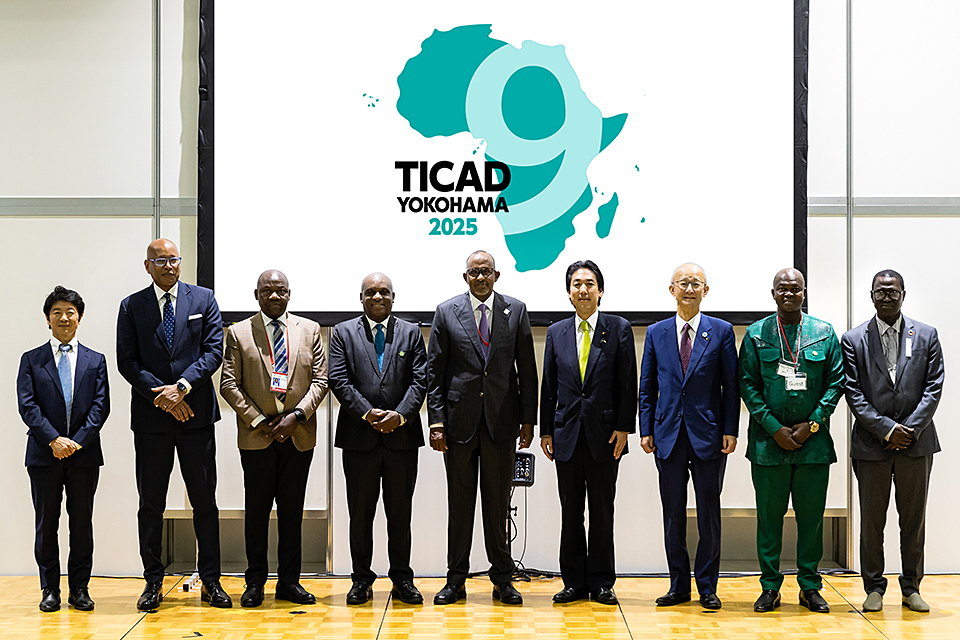
NTDs 克服に向けたアフリカとの共創 ― 産学官の連携と若者の力
8月20日:長崎大学、日本製薬工業協会、DNDi Japan、NTDs Youthの会、SDGs・プロミス・ジャパン、GHIT Fund、JAGntdの共催で顧みられない熱帯病(NTDs)をテーマとしたイベントが開催され、国会議員、製薬企業のリーダー、研究機関、若手世代、そしてアフリカの臨床専門家らがNTDsの対策に向けて一堂に会しました。
当日は、研究から医療現場への橋渡しを実現するイノベーション促進の重要性や、DNDiによる過去20年間で13種類の新薬開発の実績、持続可能かつ地域主導型の医療体制の必要性が強調されました。GHIT Fundの國井修は、NTDsの新しい製品開発には10年以上の時間と莫大な資金を必要とする一方、民間投資の誘因が限られているという資金調達の課題について指摘し、そこに新たな機会が存在すると言及しました。また本セッションでは、NTDs制圧に関する声明 「長崎アウトカム・ステートメント」に沿った、持続可能なNTDs対策へのコミットメントが再確認されました。
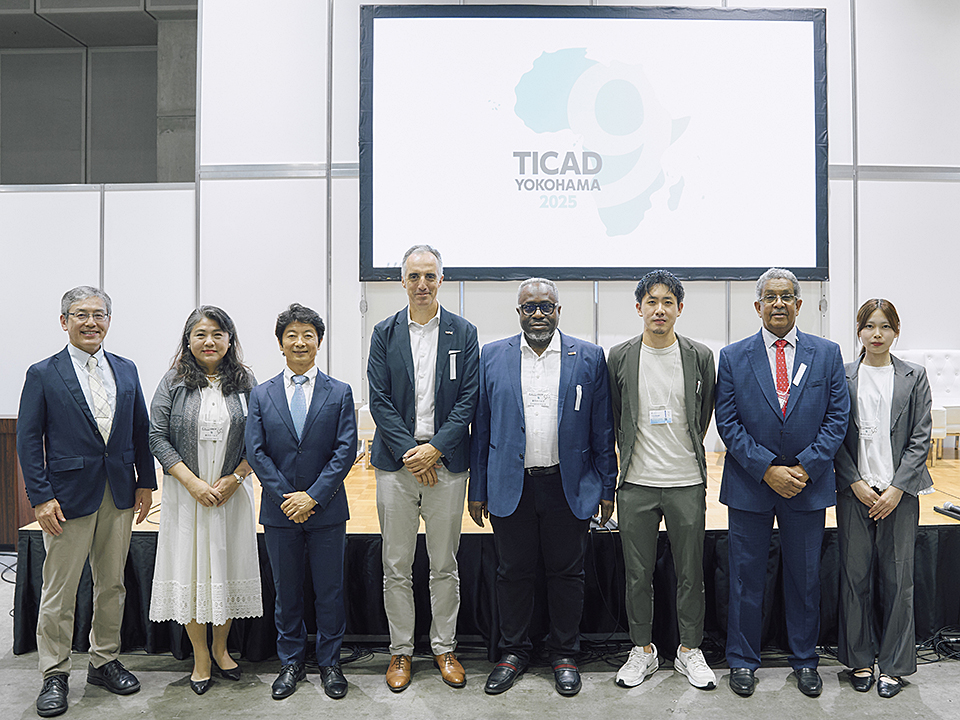
保健医療におけるアフリカ・日本 コモン・ビジョン:健康安全保障と持続可能な成長を共創する
8月21日:日本国際交流センター(JCIE)とアフリカ連合開発庁(AUDA-NEPAD)が「保健医療におけるアフリカ・日本 コモン・ビジョン」を発表、ケニア保健大臣、阿部俊子 文部科学大臣、第4回野口英世アフリカ賞受賞者のサリム・S・アブドゥル・カリム氏らが登壇しました。
コモン・ビジョンは、(1) 持続可能な保健財政と資源動員の強化、(2) 保健データシステム強化、(3) デジタル化された一次医療と予防医療の推進、(4) 研究と製品開発における共創の加速、(5) パンデミックの予防・備え・対応(PPPR)と保健システムの強化の5つの重点領域を掲げています。GHIT Fund 國井修がモデレーターを務めたディスカッションでは、持続可能な保健財政が重要な課題として挙げられ、従来の援助モデルにとらわれない、新しい税制や公平なパートナーシップの必要性が話し合われました。またワクチン・医薬品製造分野における人材育成の緊急性が強調され、進捗管理のための「スコアカード」導入も提案されました。武見敬三氏(元厚生労働大臣)は、日本とアフリカ協力がデジタル化や革新的な資金調達、民間セクターの参画を含む新たなステージに入り、アジアで進む規制調和や臨床試験の経験をアフリカでも展開できると述べました。

アフリカにおけるAMEDの取り組み
8月21日:日本医療研究開発機構(AMED)は、文部科学大臣、国内の大学や政府機関、そしてゲイツ財団の代表者を登壇者に迎え、アフリカにおける3つの主要な保健プログラムを紹介するイベントを開催しました。開発途上国における医療技術等実用化研究事業、新興・再興感染症研究基盤創生事業、地球規模課題対応国際科学技術協力プログラムが取り上げられ、AMEDが推進する複数のプロジェクトによる成果が発表されました。
パネリストとして登壇した当基金の國井修は、製品開発と産業間にある「谷間」を乗り越える課題について強調しました。早期段階での現場ニーズの認識や、世界保健機関(WHO)の戦略との連携、産業界への初期段階からの参画の重要性に言及しました。研究成果をグローバルに展開し実装につなげるために、国内外の多様なステークホルダーによる分野横断的な連携を強化する必要性を提言しました。
診断領域における課題 -人道援助の最前線から
8月21日:国境なき医師団(MSF)はアフリカ諸国における診断領域の課題を取り上げたイベントを開催しました。本イベントには、MSF、日本の外務省、WHO、アフリカ臨床検査医学会、GHIT Fundの浦辺隼が登壇しました。当日は、低所得国および低中所得国の81%が基本的な診断へのアクセスをほぼ持たない現状が指摘され、登壇者たちは「アフリカの環境に適応する診断ツール」の必要性、人材育成への取り組み、WHOの事前認証プログラムによる品質保証の重要性などが提議されました。
GHIT Fundの浦辺隼は、診断技術開発におけるGHIT Fundの役割を紹介し、「アクセスは後付けではなく、開発段階から考慮すべき」ことを強調、多層的なパートナーシップと連携による共創の重要性を訴えました。

© MSF
アフリカのワクチン研究開発・製造能力の可能性
8月22日:IAVI、国立健康危機管理研究機構(JIHS)国立感染症研究所(NIID)、GHIT Fundは、アフリカのワクチン研究と製造能力強化をテーマにしたイベントを共同開催し、VaxSen (Institute Pasteur de Dakar (IPD)の傘下企業)、アフリカCDC、IAVI、アフリカワクチン製造イニシアティブの幹部と、日本の保健医療研究の代表者たちが参加しました。討議の中では、IAVIのアフリカでの実績や、アフリカ初のWHO事前認証を取得したIPDの製造拠点など、アフリカでのワクチン製造の推進に向けた取り組みが紹介されました。
GHIT Fundの浦辺隼は同基金によるワクチン投資のうち、とりわけアフリカのパートナーと連携した3つのプロジェクト、「ブルキナファソのGRASとの妊娠マラリアワクチン開発」、「GRASとの赤血球期マラリアワクチン開発」、「ガボンのCERMELによる伝播阻止ワクチン開発」を取り上げました。さらにワクチン開発の各段階で途切れのない支援を実現するために、「数珠つなぎの資金提供者」」というコンセプトを提案し、資金不足によるワクチン開発の頓挫を回避する仕組みの重要性を訴えました。また、アフリカにおけるワクチン研究・製造能力の長期的発展を支えるために、若い世代の参画も不可欠だと述べました。
関連リンク
■IAVI:イベント概要
マラリア撲滅のための進むべき道~新薬開発を通じた支援
8月22日:Medicine for Malaria Venture(MMV)、長崎大学、塩野義製薬が、マラリア撲滅のための創薬をテーマにした官民連携イベントを開催し、ケニア共和国の政府関係者、研究者、製薬企業の経営幹部、RBM Partnership to end malariaの代表者らが登壇しました。冒頭、GHIT Fund会長の中谷比呂樹は歴史的な視点から挨拶を行い、8月22日が偶然にもロベルト・コッホが横浜を出発した記念日で、北里柴三郎による日本の創薬の歴史を想起させる日であることに言及しました。
セッションでは、マラリアが健康面のみならず、生産性・教育・家庭経済にも深刻な影響を及ぼしていることが指摘されました。また主要な撲滅への課題として、ベクター(媒介となる蚊)の生物学的変化、資金不足、気候変動を挙げました。日本の貢献例としては、長崎大学と塩野義製薬がGHIT Fundの支援を受けて開発を進める、単回投与型持続性注射剤の取り組みが紹介されました。パネルでは、アフリカを主導的な立場へと導くため、現地の状況に即した研究開発が不可欠であり、その実現においてパートナーシップの重要性が強調されました。本セッションを通じて、マラリア撲滅の実現には、研究開発の革新と現場の理解を組み合わせた、持続的かつ多国間の協力が不可欠であることが改めて確認されました。
関連リンク
■MMV:イベント概要
ステークホルダーをつなぐ:TICAD 9におけるGHIT Fundのブース出展
TICAD 9にてGHIT Fundは展示ブースを設置し、GHIT Fundの役割を幅広く紹介しました。ブースでは、国際的な官民パートナーシップとして、NTDsの克服に向けたグローバルヘルス分野の研究開発への投資(助成)の重要性を訴えるとともに、組織の体制、ミッション、具体的な活動内容を展示し、対象疾患、資金提供・申請要件などについて理解を紹介ました。これらの取り組みを通じて、GHIT Fundはグローバルヘルス分野における中核的な役割を担う組織であることを改めて示し、最も顧みられない人々を苦しめる疾病に対して協働的に取り組む姿勢を明確にしました。
今後の展望
グローバルヘルス分野は今、重要な転換期を迎えています。マラリア、結核、顧みられない熱帯病の克服には、持続的な国際協力、革新的な資金調達メカニズム、研究開発の初期段階から公平なアクセスを検討すること求められます。TICAD 9で得た成果や機運を活かし、アフリカ、日本、国際社会のステークホルダーとのパートナーシップを一層強化し、GHIT Fundのストラテジックプランの達成に向けた取り組みを加速していきます。TICADで示された協働の精神とコミットメントを、世界の顧みられない人々に影響を及ぼす疾患の撲滅につなげ、イノベーションとアクセスの推進を両輪として推進し、グローバルヘルス分野の公平性向上に持続的なインパクトをもたらすことを目指します。
参考リンク
■外務省:TICAD 9オフィシャルウェブサイト